書店に行けば山ほど並ぶ参考書。
類書を比較すると言っても、実際は子どもに取り組ませるので、親の主観で選ぶわけにもいかないし、それだけの知識も持ち合わせていない。本の前で携帯を取り出し、某通販サイトのクチコミを見て判断するより他ない・・。でも、そのクチコミは物によって「これ、評価を上げるためのサクラでしょ⁈」と感じる内容が散見されます。
本選びの際に最優先すべきは、その本を実際に使う人の直観であり、その次に大事なのは、本を使う人の性格・趣向をよく存じている人の感覚だと思います。
中学受験でいえば、
子どもの感覚>親の感覚≧先生の感覚>クチコミ
特に中学受験の場合、塾通いの人は塾から十二分に冊子が配布されていることが多く、参考書や問題集の購入を不要と感じたり消極的だったりしますが、活用していなければそれは”無い”のと同じです。なぜ活用していないか、どうして活用できていないかを突き止めるとともに、必要に応じて外部の問題集を活用されることで、入試結果も変わってきます。
せっかく買った本が書棚直行とならいために、問題集や参考書のオススメや評価を不定期に載せていきます。
さて、ここからボヤキです・・
中学受験はこの時期になりますと成績上位層と下位層で塾側の扱いが変わってきます。
一般的に塾側は全受験生に対して10~11月あたりから「特訓」や「対策」の名を冠した更なる授業追加を求めることがあります。ただし、成績上位層と下位層で特訓の意味合いは少し異なります。いわゆる一般的に想像される「特訓や対策」のイメージは成績上位層の授業です。では、成績下位層の扱いはいかに・・・
夏期講習を経て9月、10月の模試結果が低迷状況から抜け出せない成績下位層の受験生は、塾側から「お客さま」扱いを受けるようになります。とにかく塾に数多く来させて授業料を多く出してもらうスタイルです。追加授業から始まり、12月末の入試直前講習と入試日までほぼ毎日塾に通うことになります。
「お客さま」ですから少しだけ授業をして、後は自習を中心に和気あいあいと過ごして帰ってもらうことになります。塾から戻ってきた子どもの口から「よく勉強した!」と頼もしい返事を受けて、親は何となく安心します。
成績上位層の特訓、対策は塾側も本気で、難関校合格者を1人でも増やすため優秀な先生を優先的に回します。場合によっては下位層の先生も駆り出して生徒が質問しやすい環境を提供します。
成績下位層の子どもの多くは勉強自体がそこまで好きでない、もしくは何となく中学受験に取り組んでいる側面があります。だから、特訓と言えども先生が上位層クラスに駆り出されて不在だったり、時折ふらっと様子を見に来る、もしくは先生の雑談を聞く時間が多くあるような”束縛の緩い時間”が過ごせる授業形式はきっと楽しいに違いありません。
塾に行く回数が増えたにも関わらず、不満もなく日々塾に通う姿を見て、親は「やっとヤル気が出てきたのかな!」と淡い希望を抱くかもしれません。しかし、「お客さま」扱いで成績は上がるはずもなく、最終的に大半の子どもは第2志望以下の学校に通うことになります。
子どもだけでなく、親でさえも大手塾に対して絶大な信頼と安心感を持ってしまう。家庭教師を始めてから、そうした「大手塾信仰」から目覚めさせることの難しさを何度となく体感してきました。
成績下位層の子どもが毎日のように塾に通っても成績が全く上がらない状況は、客観的にみて普通ではありません。そのような泥沼状態から抜け出す唯一の手立ては「親の気づき」以外にありません。
塾からの甘い勧誘に疑念を持つとともに、子どものここ数か月の学習推移をご自身の目で確認することです。
2026年中学入試まで残り80日ほどです。
最後の2ヶ月の過ごし方を見直し、大逆転合格を達成した生徒をこれまで数多く手掛けてきました。
塾側からの「お客さま」扱いを脱して子どもに最も合った授業を徹底して行うことで、手が届かないと思われた志望校合格が可能となります。
ご相談をご希望される方はブログまたはホームページからお気軽にどうぞ!
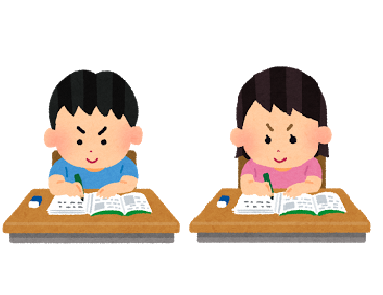
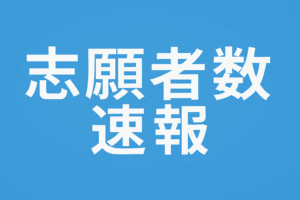

コメント